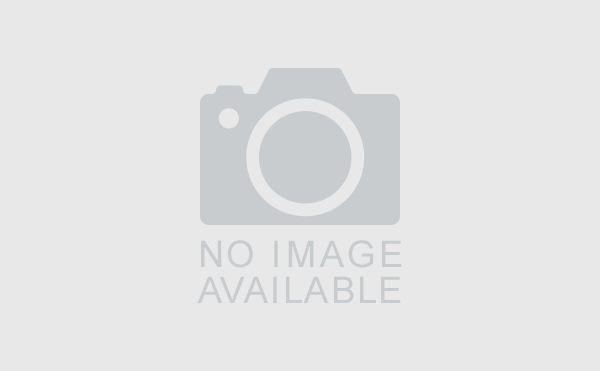プラスチック製品の回収が始まったが・・・⁉
4月から横浜市全区でプラスチック製品の回収が始まりました。磯子区では昨年10月からモデル実施されていました。ヨコハマプラ5.3(ごみ)計画では、燃やすごみに含まれているプラスチックごみを2030年度までに2万トン削減するということです。(2022年度比)これは1人当たり年間5.3㎏になります。市によると、ごみ処理に伴って発生するCO₂の約90%がプラスチックなど石油由来のごみの焼却により、燃やすごみのうち7.9%がプラスチック類ということです。
この施策は、国が2021年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を制定し、2022年4月から施行したことによります。廃プラスチック有効利用率の低さや海洋プラスチック等による環境汚染が世界的な問題となっていること。さらに日本は世界3位のプラスチック生産国で、1人当たりの容器包装廃棄量は世界で2番目ですが、アジア各国へ輸出することができなくなった(ごみの輸入規制強化)という背景があります。国の計画では、2030年までに使い捨てプラスチックを25%排出抑制し、2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により有効利用するとしています。製造業者には長持ち・リサイクルしやすい製品が推奨され、自治体には家庭から出るプラスチックごみの収集が求められます。この目標は諸外国に比べて低いのではと思います。
EUでは2021年にプラスチック製品や発泡スチロール製の使い捨て容器の流通を禁止しています。中国は以前は廃プラスチックを受け入れていて、日本のプラスチックごみの主な輸出先でしたが、2017年に輸入禁止を法制化、現在はプラスチック袋や一部のプラスチック製品の使用を禁止しています。アフリカ諸国は都市の急激な人口増加より廃棄物量も増加が予想され、54カ国中30カ国でプラスチック袋が禁止されています。
日本の法律の問題は名称でわかるように「循環」の促進だという点です。新しい技術の

容器包装プラスチック+プラスチック製品
開発に期待するところが大きい過ぎると思います。環境汚染、気候変動、化石燃料の枯渇など現状のひっ迫した問題に真剣に向き合っていないと感じます。
容器包装リサイクル協会の資料によると、自治体から再商品化を委託された容器包装プラスチックの再商品化率はこの10年間65~67%で、リサイクル技術が進歩しているとは思えません。委託量は自治体で手作業で異物を取り除いた後の量で、家庭からの排出量ではありません。ガラスびんは商品化率95.7%(2024年度)です。プラスチックのリサイクルは容易ではありません。製造や販売の規制が必要なのではないかと考えます。