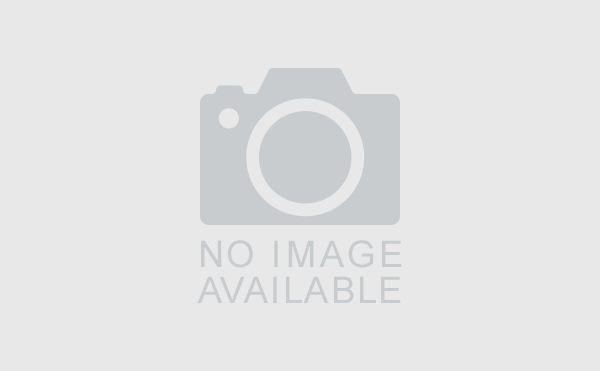外国籍市民と共に生きる社会
神奈川人権センター主催の人権学習会「在日外国人にかかわる住民施策 アンケートの集約結果報告について」に参加しました。
横浜市の外国籍市民の人口は131,223人(2025年4月)で、10年前の約1.65倍です。国籍については、10年前は中国、韓国が9割近くを占めていましたが、現在は多岐に渡っています。小学2年生の私の孫の一番の仲良しはネパール人です。市は「横浜市多文化共生まちづくり指針」を策定し、「多様性・包摂性に富み、誰もが活動できる共生社会」の実現を目指すとしています。しかし、市民生活に大きくかかわる行政職員のうち外国籍職員はわずか17人(2024年)です。外国籍市民は人口約377万人に対して約3.5%ですが、職員数は46,000人に対してわずか0.037%です。
また、外国籍者の任用については制限を設けている自治体が多く、横浜市でも衛生監視員、消防区分や昇進について制限しています。これは1953年に内閣法制局が示した見解を根拠としています。「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解するべきである」というものです。そのため募集要項の国籍条項を撤廃しても、ほとんどの自治体がこの見解に基づいて消防職員などに制限を設けています。しかし、越前市はブラジル人コミュニティがあり、ポルトガル語がわかる人がいないと業務に支障をきたすため、ブラジル人を消防職員に採用しているそうです。
川崎市では「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定しました。インターネット上を含めた公共の場所での不当な差別的言動を禁止する罰則規定のある条例です。また、外国人市民代表者会議を設置し、外国人市民の市政参加を推進しています。
通訳ボランティアをしている会員から、「少子高齢化による労働人口不足で外国人の受け入れ規制を緩めるのであれば、それ相応の仕組みづくりが必要だ。学校や公共施設などでの通訳はボランティアに丸投げになっていて、現場は悲鳴を上げている。外国人に対する日本語教育も個人ボランティアの日本語教室任せで、週に1~2時間の語学教育で修得はできない」という意見が寄せられました。国は2019年に「日本語教育の推進に関する法律」を制定し、「日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本後教育を受ける機会が最大限に確保される」ことを基本理念としています。しかし実態はまだまだお粗末なようです。
多様性、公平性、包摂性を基本理念として、横浜市は国の対策を待つのではなく、その実情に合わせて地域のNPO・NGOや市民と連携して積極的に独自施策を推進するべきです。外国籍市民を単に労働力と見なすのではなく、豊かな地域社会をつくる担い手の一員として尊重することが大切だと思います。