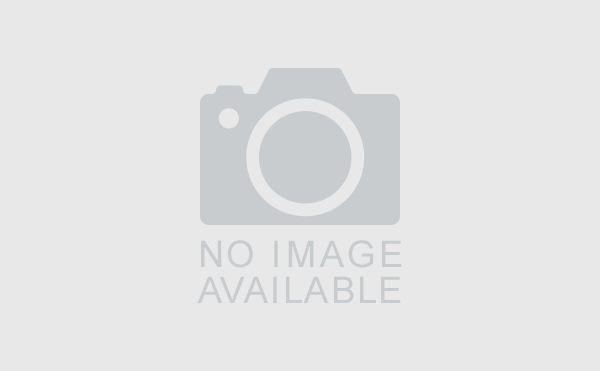子ども・若者が豊かに生きられる社会をつくる
国際協同組合年フォーラム「協同組合発、子ども・若者が豊かに生きられる社会をつくる」に参加しました。基調講演として、北九州市でNPO法人抱樸を主宰し、居場所のない人たちの伴走支援に長年取り組んでこられ、牧師でもある奥田知志さんのお話をお聞きしました。誰からも存在を認められない境遇で生きてきた人が、「どうでもいいいのち」から「残念ながら死ねない」と思えるまでの様々な困難を聞き、人は他者とのつながり、信頼関係がないと生きられないと思い知りました。
パネリストのひとり西野博之さんは、認定NPO法人フリースペースたまりば理事長で、川崎市の「子どもの権利に関する条例」の制定に向けて、当事者である子どもたちの意見を聞く様々な場を設け、実効性のある条例になるよう尽力されてきました。条例の具現化をめざす「子ども夢パーク」で、「安心して失敗できる」「正しさ、完璧を求めすぎない」「生きているだけで祝福される」自己肯定感を育む居場所づくりに取り組んでいます。今や不登校は35万人です。学校制度そのものを問い直す時期にあるのではないかということです。
元文部省官僚の前川喜平さんは、教育制度について積極的に提言を発信されています。日本の教育は戦前からの国家のために役立つ人材、兵隊をつくるという流れが今も続いてると言わざるを得ません。学校教育は地方自治法上の位置づけでは「自治事務」であり、文科省からの発信は「指導・助言」の範囲の筈です。しかし実態は、文科省→県教委→市町村教委→学校へと縦の支配になっています。子どもたちの幸福度、自己肯定感が低く、自殺者が増えています。子どもたちも教師も生きづらい学校で、不登校・病気欠席、病気休職(心の病気、鬱)が増えています。そんななかで、学校は本来地域のものであり、当事者の子ども、教師、保護者、地域住民が学校運営に大きく関わるコミュニティスクールの取り組みが広がっています。
以前「夢みる校長先生」という映画を見ましたが、校長先生の裁量で、通知表なし、宿題なし、テストなし、校則なしなどを実施した7つの公立小中学校の校長先生の取り組みが紹介されています。いずれの校長も教育委員会等から何か苦言を言われたことはないそうです。でも校長先生が代わると元に戻ってしまう事例が多いようです。
オランダからオンラインで参加された教育研究家のリヒテルズ直子さんからは、子どもたちを民主的社会の担い手と位置付けるオランダのシチズンシップ教育について伺いました。子どもはいずれも大人と同じ有権者であり、比護や加護は子どもたちの自由や自立を育てない、他者の自由を尊重することで自分の自由が保障されることを言葉ではなく、実践の場で経験し学びます。高校生の全国自治組織があり、生徒の声を政治、メディアや教育の場に届け、試験制度への苦情も受け付けます。教師と生徒の関係はフラットで、個人面談は教師と生徒で行われ、保護者の出番はありません。
横浜市は昨年6月に「横浜市こども・子育て基本条例」を制定しましたが、条例文には「権利」という文言が一切明記されていません。「その年齢及び発達の程度に応じて」という言葉が頻繁に出てきます。条件付きのように聞こえます。また、教育委員会に教育行政監を置き、組織内の不祥事に対するリスク管理を強化しています。さらに約50人体制の「不登校支援・いじめ対策課」を新設しました。500校を超える小中学校に50人でどう対応するのか、現場の教師への監視体制になるのではないかと懸念します。真っ先に実施するべきは、現場の教師不足対策・待遇改善ではないでしょうか。
学校教育に関する課題は山積していますが、自治体で、各学校でできることも多々あります。長野県の「信州学びの円卓会議」など、新しい試みが進んでいます。フォーラムでは、「協同組合立の学校」という話も出ました。自由な発想で学校を考えてみることが大切だと思いました。