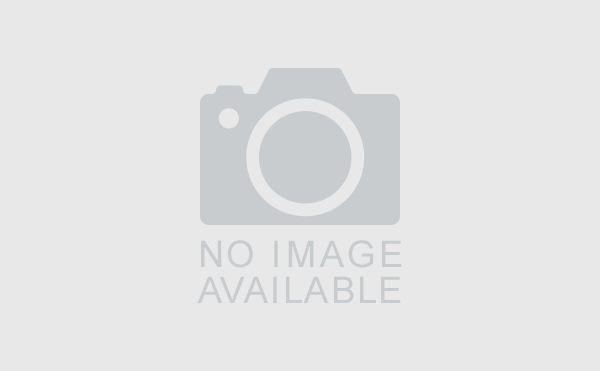介護保険を立て直すために!
「介護を崩壊させない実行委員会」の「介護フォーラム2025 介護保険を立て直す!」をオンラインで視聴しました。2000年に始まった介護保険制度は25年目となり、3年ごとに改定がされて「負担増と給付抑制」が繰り返されてきました。
65才以上の高齢者の割合は、2000年の介護保険制度創設時には17.4%でしたが、2004年10月1日時点では29.3%となっています。今後も増え続けると予測されています。また、高齢夫婦のみの世帯や高齢単身者が増え、介護サービスの需要は増々拡大します。厚生労働省によると、必要な介護職員数は2026年度には約240万人(2022年度比+約25万人)、2024年度には約272万人(+約57万人)となっています。ところが、2024年の改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられ、2024年の介護事業者の倒産は過去最多の172件、そのうち訪問介護事業者が81件で、訪問介護の人材不足が大きな問題となっています。特に小規模事業者の経営が厳しくなっています。政府は大規模化で効率化を図るという意図のようですが、訪問介護は在宅福祉の重要なサービスであり、小規模事業者が地域福祉を支えている現状を考慮するべきです。訪問介護だけでなく総じて介護職の給与は、他の業種に比較して低いと言われています。人材確保のためには、介護職の社会的役割と意義にふさわしい基本報酬を保障する必要があります。
要介護1・2を総合事業に移行しようとする動きがあります。2015年から要支援1・2が市町村の総合事業となりましたが、事業目的を達成できていない市町村が多く、要支援者へのサービス低下が危ぶまれています。報酬単価が低いため担い手が広がらず、大手事業者が受託しないので、小規模事業者に回ってくるという話も聞きます。総合事業そのものを見直し、要支援者も含めた在宅サービスの在り方を再検討するべきです。
利用者負担の引き上げについては、現在の物価高の状況であり得ない話です。サービスの利用控えにつながり、重度化が進み、家族等介護者の負担が増大し、介護離職が懸念されます。資産を考慮した負担という意見もあるようですが、個人資産をどのように把握するのでしょう。
ケアプラン有料化についても同様です。利用抑制につながります。制度創設当初、税による措置ではなく保険制度になることで、利用者がサービスを選べると言われました。利用者の立場に立ったケアプラン作成は介護保険制度の要です。
高齢者福祉事業を実施しているNPO法人でケアマネをやっている知人に聞きました。「ケアマネが5人いるがいずれも60才以上、やや70才に近い状況で、新しい若い人は入ってこない。地域では高齢化が進み、要支援者が急増しているが、ケアマネ不足で6カ月待ちの人が出てきている。」ということです。
政府は給付を抑制して制度を維持しようとしていますが、制度があっても使えなければ意味がありません。現状を直視し将来を見据えて、適切な税負担増を検討するべきです。