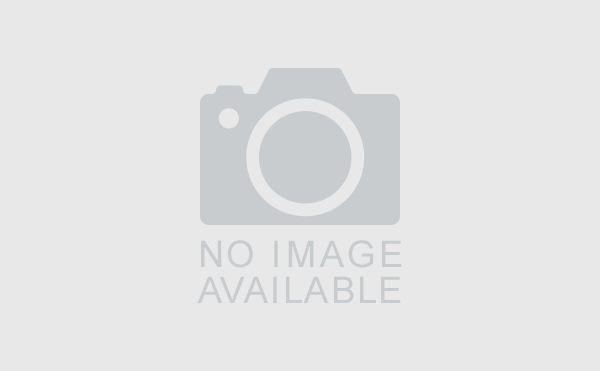戦争をさせないために!
「すべての基地にNOを・ファイト神奈川」主催の望月衣塑子さんの講演に参加しました。
望月さんの到着が遅れたので、その間に基地監視団体「リムピース」の星野潔さんから、NATOなどアメリカ同盟国艦船の横須賀・東京への入港の動きにつて報告がありました。8月のイギリス軍空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の入港は話題になりましたが、その他にもスペイン、オーストラリア、イタリア、フランス、ニュージーランド、カナダ、シンガポールなどの艦船が次々と横須賀港に入港しています。日本列島が欧米諸国の対中包囲網の前進基地になっているような状況です。米軍基地への米軍以外の艦船の寄港の法的根拠には疑問があります。国連軍地位協定なのか?外務省や横須賀市に説明を求めても判然としない状況で、文民統制の箍(たが)が外れているのではないかと懸念されるということです。
望月さんのテーマは「もがみ型護衛艦『共同開発』どうなる武器輸出」ということでしたが、話は軍備増強についてはもちろん、自民党総裁選、参政党の躍進、メディアの役割など多岐に渡りました。
2022年12月に岸田政権は、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」のいわゆる安保三文書の改定を閣議決定しました。これにより「敵基地攻撃能力」の保有・活用が可能になりました。憲法9条の下で、これまでの「武力行使は必要最小限に限られ、相手国の領域に直接的な脅威を与える攻撃的兵器の保有は許されない」といういわゆる専守防衛の憲法解釈に反するものでした。2023年6月には、「防衛財源確保法」が成立し、日米一体化した軍備増強は着々と進んでいます。オーストラリアと共同で最新鋭の「もがみ型護衛艦」を開発し、オーストラリアへの輸出を官民一体で目論んでいます。今年4月から3年かけて先制攻撃用の巡航ミサイル「トマホーク」400発を購入することを決定し、呉、佐世保、舞鶴、横須賀の海上自衛隊に配備されます。横須賀では米軍の指揮の下で運用訓練も始まりました。全国の自衛隊基地を始め関連施設の整備も進んでいます。一方で、国立大学への交付金は減額され、東京芸術大学では産学協同研究など外部資金の導入が困難で、練習用のピアノを売却する事態になっています。
防衛費は、1976年の三木内閣が軍事大国化の歯止めとしてGDP比1%枠内を決定、1987年の中曽根内閣は1%枠を撤廃しましたが、その後も「1%」を大きく超えることはありませんでした。ところが、ロシアによるウクライナ侵攻以来、NATOの動きに同調し、2027年度には2%以上にするとしました。2026年度の概算要求は過去最大の8.8兆円です。トランプ大統領は、新しい首相が決まったら訪日すると言っていますが、武器の輸入や「思いやり予算」の増額などを強要してくることが懸念されます。ウクライナやパレスチナの状況を見れば、一旦戦争が始まってしまえば泥沼であり、終結するのがいかに困難であるか思い知ります。メディアの報道も軍備増強に対する危機感が希薄で、当たり前のように「抑止力」を語ることが多い状況です。大規模災害や外部からの武力攻撃の際に社会秩序を維持するために、基本的人権を制約する「機緊急事態条項」が必要だとする動きもあります。軍事力ではなく外交による対話を粘り強く続けることが大切です。「おかしい」と思うことには積極的に意見表明し行動していくことが、「戦争をさせないために」必要だと改めて思いました。