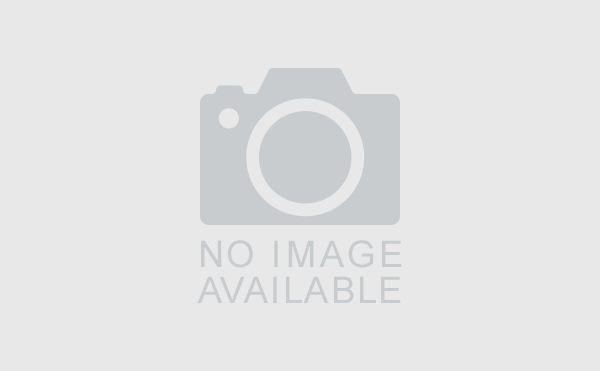憲法カフェ 憲法とは?人権とは?平和とは?
生活クラブの憲法カフェに参加しました。講師は川崎合同法律事務所の川岸卓哉弁護士です。28人の参加があり、活発な意見交換が行われました。
テーマを決めて、それに関する条文を探すということから始まりました。まずは憲法を守らないといけないのは誰か? という問いに対して、99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となっていて国民は含まれていません。法律は国民の自由を制限して、社会秩序を維持するためのものですが、憲法は国家権力を制限して、国民の人権を保障するものだということです。憲法で定めている国民の義務は3つ、26条2項 子供に教育を受けさせる義務、27条 勤労の義務、30条 納税の義務 です。権力に憲法を守らせるために、国民はどうしないといけないか? 12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とあります。不断の努力?大変そう!
人権については、いろいろな裁判の事例をもとに議論しました。まずは婚外子相続差別については、最高裁は、民法900条4号の「婚外子の遺産相続分は結婚している男女間に生れた子の半分」という規定は、憲法第14条の「法の下の平等」に違反し、無効であると判断しました。
同性婚については、14条の「法の下の平等」と24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」等の条文を根拠に、地裁、高裁では各地で違憲判決が続いて、最高裁の判断が待たれています。
夫婦別姓につては、2015年の最高裁判決では違憲となりましたが、裁判官のなかには反対意見もあり、「改姓は女性に集中していて実質的に不平等を強いており、13条、24条の個人の尊厳を侵害している」と指摘しています。「価値観の多様化に対応し、将来的には選択制夫婦別姓制度の導入が望ましい」という補足意見もありました。
東京都教育委員会の「日の丸・君が代」を強制する通達は違憲・違法だという訴えについて、東京地裁は19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」を根拠に、起立・斉唱を拒否する自由があると判断しました。しかし、最高裁では、反対意見もありましたが、敗訴しました。
個人の自由と自由がぶつかったとき、どう調整するか? 13条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。」とあります。「公共の福祉」とは何かが大きな問題です。少数者や弱者を排除することがあってはならないとオモイマス。
袴田さんの冤罪については、31条 無罪法定主義、32条・33条・35条 裁判所による裁判と逮捕、差し押さえチェック、34条・37条 対等に争えるように弁護人依頼権、36条・38条 拷問、自白の強要禁止、39条・40条 無罪の場合の一時不再議・賠償等に反するもので、国家権力の国民に対する横暴の最たるものです。
平和については、自衛隊は違憲か? 9条を普通に読めば違憲だと言わざるを得ません。1973年の長沼ナイキ基地訴訟で原告は、「自衛隊は陸海空軍に相当し違憲」「基地が建設された場合、有事に敵国軍の攻撃目標とされ、憲法前文の『平和のうちに生存する権利』が脅かされる危険がある」と主張しました。地裁では違憲判決を下されましたが、高裁では裁判所は政治的な判断を避けるべきとして一審判決を破棄、最高裁では憲法に触れず、原告の訴えの利益なしとして上告を棄却しました。政治や司法内部からの圧力が問題になりました。
2015年には集団的自衛権の行使を要認し自衛隊の活動範囲を拡大する「安保法制」が提示され、大きな反対運動が展開されました。成立後も各地で「安保法制違憲訴訟」が起きましたが、最高裁は憲法判断を回避して上告を退けました。しかし、訴訟は全国で継続されています。
その後も2022年には、安保3文書が閣議決定され、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅な増額などが明記され、平和憲法を蔑ろにした軍備増強が続いています。
ロシアによるウクライナ侵攻以来、平和のために軍隊は必要かではというムードが広がっているように思います。しかし、世界各地の戦争や紛争を見ても軍備増強による抑止力はあり得ません。
この日集まった人たちがそれぞれの課題に対して深く考え、また行動されていることに感銘を受けました。この憤りをどのように力にしていけばいいのか。粘り強く声を上げ続けていきたいと思います。

会場に掲示された憲法9条キルト(日高佳子さん作)